私が受験したときの話をしますと、
午前中に『法適合確認』のテストが3時間行われ、休憩が1時間15分あります。
その後、午後に『構造設計』のテストが3時間行われます。
めちゃくちゃ疲れます。
休憩時間が設定されている分、製図試験よりはマシに感じましたが。。。
【前日までに準備すること】
テストには以下の物が持ち込め、利用できます。
・講習テキスト、講義用スライド
⇒過去問を解き、気になったところに付箋をつけるなどしましょう。
持参を忘れるととても厳しいです。
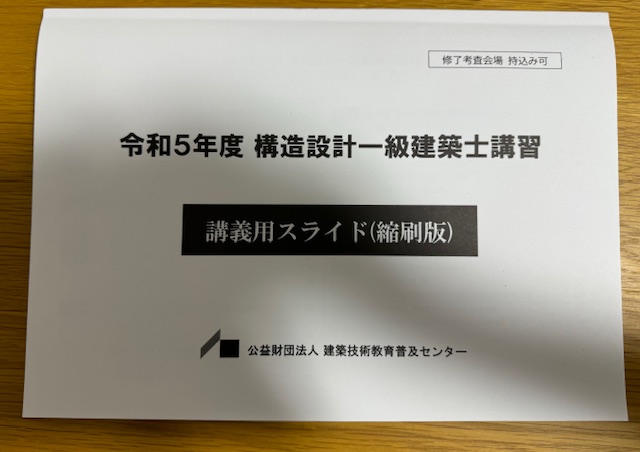
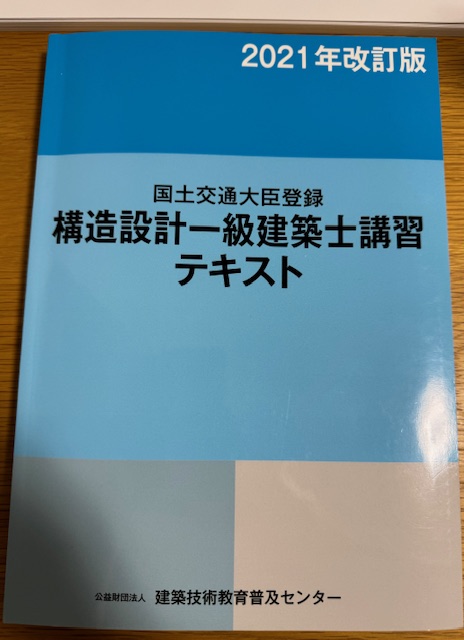
・黄色本
⇒過去問を解き、気になったところに付箋をつけるなどしましょう。
同じく、持参を忘れるととても厳しいです。
・関数電卓(プログラム機能のない物)
一応、2つ持って行ってもいいかもしれません。
私は2つ持っていきました。
携帯電話・スマホを使うことはできませんので、
関数電卓がないと絶望的です。
・定規
私が受験したときはブレース接合部の補強に関するスケッチが求められました。
必要に応じ、テンプレートを持って行ってもよいでしょう。
【当日、テスト前に行うこと】
過去問を解いていく中で、間違えやすいことが分かっていれば、
そこの最終確認をすることをおススメします。
また、腕時計の持参をお勧めします。
【テスト中に行うこと】
テストは両科目とも『理由記述付き 4 肢択一式』×10と『記述式問題』×3で構成されていました。
■『4理由記述付き 4 肢択一式』
基本的に最も不適当なものを選び、その理由を記述します。
理由を記述するときに、注意していただきたいことがあります。
それは、
【テキストや黄色本の言葉をそのまま使う】
です。
黄色本を読み、自分の言葉で解答を構成してしまうと、
原文と微妙に意味が変わってくる可能性があり、
減点される可能性があります。
理由記述では文字数制限がないため、
可能な限り原文のまま、解答することをおススメします。
■『記述式問題』を解くとき
最初にすべての問題を確認し、
時間配分を設定し、
必ず白紙の大問が発生しないようにしてください。
なぜなら、合否判定に科目ごとの足切りが設定されているからです。
受講要領には
[記述式 3 問について、問題ごとに一定以上の評価が得られ]
と記載されています。
あとは力の限り問題を解くだけです。
いかがでしたでしょうか。
これから受験する方の参考になれば幸いです。
“④構造設計一級建築士のテスト前日・当日にすること” への3件のフィードバック
[…] ①概要②勉強スケジュール ③修了考査の勉強法④テスト前日・当日にすること⑤合格発表から免許が届くまで […]
[…] ③構造設計一級建築士 修了考査の勉強法 ④構造設計一級建築士のテスト前日・当日にすること ⑤構造設計一級建築士 合格発表から免許が届くまで […]
[…] ④構造設計一級建築士のテスト前日・当日にすること 前へ 次へ […]