こんな人に読んでほしい
これから技術士試験の勉強をする方
勉強を頑張ったけどダメだった方
採点基準が知りたい方
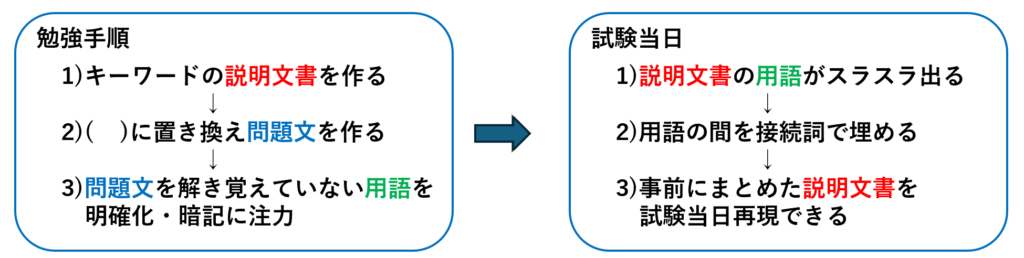
技術士二次試験の筆記試験を受験しようとする方は、
何かしら勉強してから望むと思います。
ここでは、合格したとき、実際に私が行った勉強方法をご紹介します。
(各科目の得点率は71~80%でした)
「勉強時間をとったのにダメだった」といった方がいらっしゃれば、
参考になれば幸いです。
■目次
- (おさらい)筆記試験の概要
- 得点の高い答案とは
- なぜ、テスト当日にキーワードを盛り込んだ文章が書けないか
- できることとできないことの境界を明確にする勉強方法
- 題意に沿った解答を意識する
- 答案に記載すべきコンピテンシー
- 他の記事の紹介
■(おさらい)筆記試験の概要
筆記試験は、
①2時間で1800字の論文を書く必須科目(Ⅰ)
②3.5時間で3600字の論文を書く選択科目(Ⅱ-1 Ⅱ-2 Ⅲ)
があります。
問題が与えられ、その題意に沿った解答を行う必要があります。
例えば建設部門のⅠとⅢですと、「国土交通白書」など、
国の方針に沿って解答する必要があります。
また、Ⅱ-1、Ⅱ-2では、種々の専門書をまとめて覚えておくと思います。
■得点の高い答案とは
ここで得点の高い答案とはどういう答案でしょうか。
多くの本に書かれていることですが、
- キーワードが盛り込まれていて
- 題意に沿っており
- コンピテンシーを意識した
答案のことです。
■なぜ、テスト当日にキーワードを盛り込んだ文章が書けないか
多くの受験生は、「国土交通白書」や「キーワード集」などを読み、
もしくは音声データを聞いたりして、内容を覚えて試験に臨んでいると思います。
しかし、テスト当日、試験用紙を前にすると、
準備したキーワードが『書けない』
ということがあると思います。
準備したキーワードが書けないとどうなるか、
接続詞などを多用し、間延びした解答を作成することになります。
そういった解答は、採点官から合格点をもらえないでしょう。

■テスト当日に書けるようにするには
仮に練習で1800字の論文を手書きで書いたとして、
間延びした解答だったとしましょう。
それでもあなたは、「ああ、よく書けた」と思います。
書こうと思っていたキーワードの7割くらい書けていて、
文字数が埋まっていたら合格だと思ってしまいます。
私もそうでした。
自分の答案を客観的に採点するのは難しいのです。
ひたすら書く勉強・読む勉強・聞く勉強のみを行うことの何がいけないのか。
それは、
『自分が書けることと書けないことの境界が曖昧である』
ためです。
なので、以下の図のように段階的に勉強方法を変えるとよいと思います。
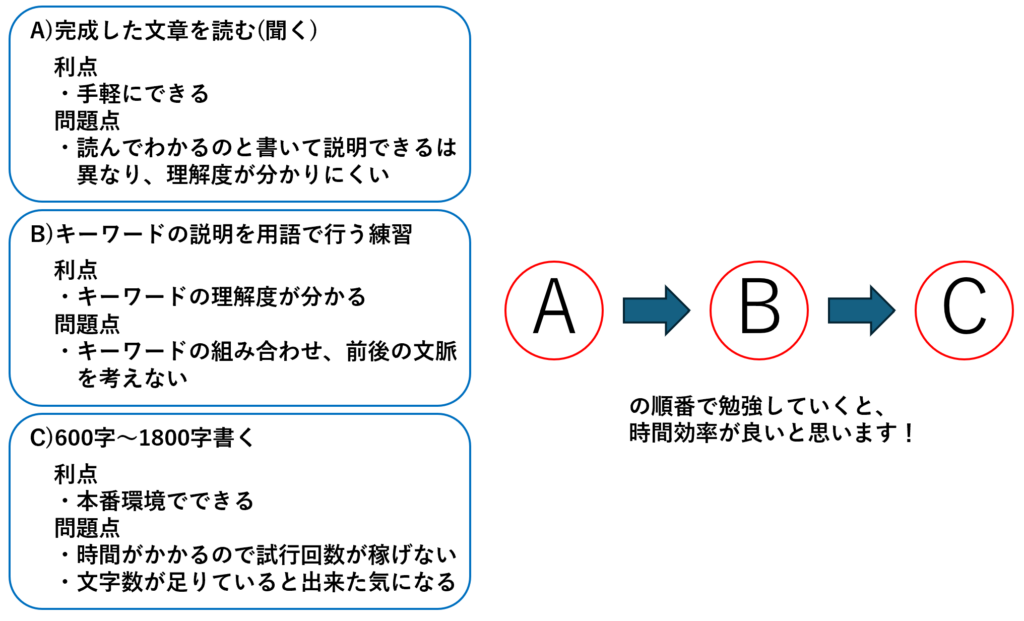
また、Cの通しで書くことの問題点、それは、
10個キーワードを用意する⇒6個は書けて、4個は書けない
その違いはとても分かりにくいものです。
書けない4個のために、10個のキーワードを何度も練習するのも非効率的です。
なぜなら6個はすでに覚えていますから、
覚えていない4個のために、2.5倍の労力を費やすことになります。
できないことだけ練習する。
これが限られた時間で合格するために意識すべきことです。
■できることとできないことの境界を明確にする勉強方法
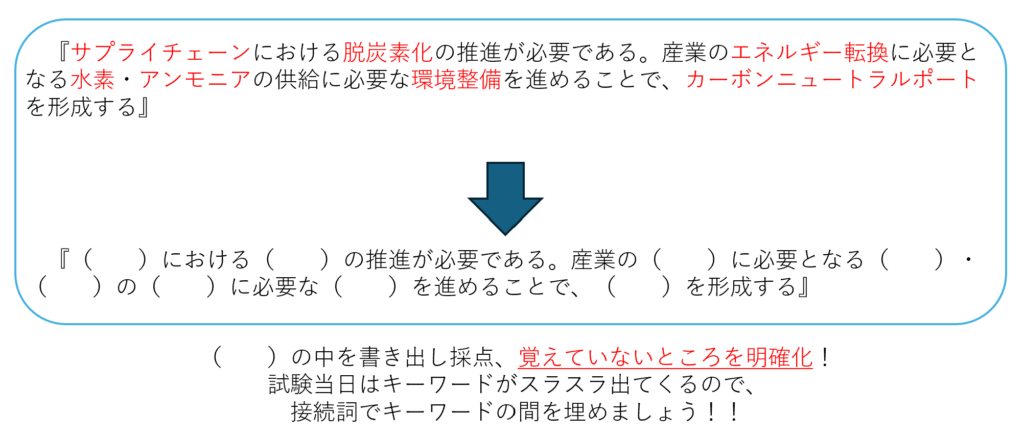
私は
①まず、キーワード毎にその意味をまとめます。
②まとめた文書のうち、重要である箇所を( )表記とする。
③( )表記の個所を正確に回答できるように何度もoutputを繰り返す。
という勉強方法を行いました。
具体例を出すと、
<原文>
カーボンニュートラルポート
『サプライチェーンにおける脱炭素化の推進が必要である。産業のエネルギー転換に必要となる水素・アンモニア
の供給に必要な環境整備を進めることで、カーボンニュートラルポートを形成する』
という文書を覚えようとします。
⇩これを加工し
<暗記用>
カーボンニュートラルポート
『( )における( )の推進が必要である。産業の( )に必要となる( )・( )の( )に
必要な( )を進めることで、( )を形成する』
という文書を作ります。
主語も述語も隠れているため、暗記用だけ見ても何もわかりませんね。
ですが、暗記用の文書をみて、( )の中をすべて書き出せるようになれば、
試験当日、「覚えたはずだけど出てこない」といったことはなくなり、
キーワードをもとに文書を作成できるはずです。
■題意に沿った解答を意識する
これは、ひたすら知識をつけるしかないという面もあります。
キーワード毎の関連性を意識してまとめておきましょう。
具体的には、
『地震⇒2016年の熊本地震』
『水害⇒2018年の岡山、内水氾濫』
『人手不足⇒1996年と2016年の建設業労働者の違い』
といった解答をあらかじめ用意しておきましょう。
■答案に記載すべきコンピテンシー
私が考える、各試験科目の設問と、コンピテンシーの関係を記載します。
必須Ⅰ
1) 設問1 【専門的学識】【問題解決】をアピール!!
2) 設問2 【問題解決】をアピール!!
3) 設問3 【評価】をアピール!!
4) 設問4 【技術者倫理】をアピール!!
選択科目Ⅱ-1
1) 設問 下記の種類があります 【専門的学識】をアピール!!
- 次の〇〇〇の中から1つ選び、~における留意点を述べよ。
⇒不具合などに使われる文章です。業務を進めるうえで生じうるエラーを予見し、あらかじめ調査することを求めています。 - 次の〇〇〇の中から1つ選び、~における概要と特徴を述べよ。
⇒単純な説明問題です。『概要』は辞書的な意味を、『特徴』は似ている他の物との差を説明する必要があります。 - 次の〇〇〇の中から1つ選び、~について対策を述べよ。
⇒『不具合を未然に防ぐための行動』を述べる必要があると思います。留意点は事前の調査に近い内容、対策では調査に基づいた行動、
というイメージがあります。
選択科目Ⅱ-2
1)設問1 【専門的学識】をアピール!!
2) 設問2 【マネジメント】をアピール!!
3)設問3 【リーダーシップ・コミュニケーション】をアピール!!
選択科目Ⅲ
1) 設問1 【専門的学識】【問題解決】をアピール!!
2) 設問2 【問題解決】をアピール!!
3) 設問3 【評価】をアピール!!
※下記の私の電子書籍では、より詳細に解説し、筆記全科目70%以上の得点で合格したときの
私の本試験での骨子(必須Ⅰ)なども載せています。
良ければ購入を検討していただければと思います。
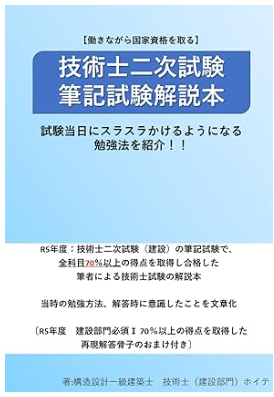
他の記事の紹介
いかがだったでしょうか。
他の記事ではオススメの書籍などを紹介していますので、
ぜひ、ご覧になってください。
“⑥技術士(二次試験) 筆記試験の勉強法・コンピテンシーと採点基準” への16件のフィードバック
[…] ⑥技術士(二次試験) 筆記試験の勉強法 前へ 次へ […]
[…] ⑥技術士(二次試験) 筆記試験の勉強法 […]
[…] ⑤技術士(二次試験)実務経験証明書の添削は必要か? ⑥技術士(二次試験) 筆記試験の勉強法 ⑦技術士(二次試験) 筆記試験当日の流れ […]
[…] ⑥技術士(二次試験) 筆記試験の勉強法 前へ […]
[…] ⑥技術士(二次試験) 筆記試験の勉強法・コンピテンシーと採点基準 […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] ⑥技術士(二次試験) 筆記試験の勉強法・コンピテンシーと採点基準 […]