※この記事およびリンク先はPRを含みます。
こんな人に読んでほしい
選択Ⅲの課題の書き方がわからない方
課題の内容をどう書けばわからない方
問題と課題の違いがわからない方
観点に何を書けばよいかわからない方
これを読めば、合格答案の構成を理解できます!
筆者は技術士筆記試験を選択80%の得点で合格しました。
その時、考えたことを記事にしましたので皆さんの参考になれば幸いです。
目次
- 選択Ⅲ(1)の構成
- どのくらいの文章を費やすべきか
- 問題と課題の違い
- 1.抽出すべき課題
- 2.それぞれの観点を記載する
- 3.課題の内容を示す
- 筆者が不適当と思う課題
- 筆者が思う(1)の答案構成
- 他の記事のご紹介
選択Ⅲ(1)の構成
選択Ⅲの(1)はおおむね以下のような書き出しです。
【〇〇を進めるに当たり、技術者としての立場で多面的な観点から3つ課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、課題の内容を示せ】
ここでは、3つの指示をされ、受験生に行動を求められています。
- 多面的な観点から3つ課題を抽出する
- それぞれの観点を明記する
- 課題の内容を示す
これらは漏らさず記載する必要があります!
どのくらいの文章を費やすべきか
選択Ⅲは全1800文字・3ページとなっています。
そのすべてを(1)に費やしてしまうと不合格になるでしょう。(試したことはないけど)
筆者の感覚からお話しすると、
600文字・1ページを(1)に費やすのがおススメです。
そうすると、構成としては、
課題1つにつき説明文が150文字前後になると思います。
なので私の1ページ目は、
1.〇〇のための課題
(1)課題A 【タイトル+6~7行】
(2)課題B 【タイトル+6~7行】
(3)課題C 【タイトル+6~7行】
としました。
問題と課題の違い
ここでこれから受験する皆さんは、【問題】と【課題】の違いを説明できるでしょうか。
【問題】は英語でいうと【ploblem】で、
【課題】は英語でいうと【subject】もしくは【theme】と訳されます。
理想とする状態があるが現在その理想からかけ離れているとすると、
それは何らかの弊害、いわゆる【問題】が生じています。
理想とのギャップを問題 ととらえると良いと思います
その【問題】を取り除くのが【課題】の実行です。
なので、
3つ課題を抽出しろ、
と問題文に書いているのに、現在の問題を書いてはいけません。
例えば、
予算が足りない・人が足りない、
などですね。
1.抽出すべき課題
理想とする状態と現在を埋めるために設定するものが課題である、
と説明しました。
それでは、実際、どのようなことを書くと良いか説明します。
具体的には、
【国の指針】
を書くのが良いでしょう。
問題が、『人手不足である』とすると、
『DXによる生産性の向上』が課題となります。
そういったものを3つ記載すればよいのです。
建設部門であれば、国の指針である国土交通白書や、
その読み方を利用し、あらかじめ、
問題と課題の関係性を整理しておくと良いと思います。

【国土交通白書の読み方】 ←クリックでAmazonのページに飛びます
2.それぞれの観点を記載する
『それぞれの観点を記載せよ』と言われても、
何を書けばよいのかわからないと思います。
そういった方は、〇〇性 という言葉で統一してみると良いと思います。
私は、『安定性』といった言葉を3つ使いました。
ちなみに、下で紹介する本では、それぞれの観点に記載すべき事項として、
〇〇性
という言葉を使うことを推奨しています。
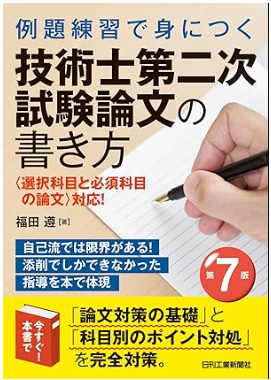
【技術士第二次試験 論文の書き方】 ←クリックでAmazonのページに飛びます
書籍の中では、20種類以上が紹介されていますので、
受験生の方の参考になると思います。
3.課題の内容を示す
技術者としての立場で課題の内容を示すことが求められています。
具体的には、
現状⇒その問題⇒課題⇒効果
くらいを6~7行で書けばよいと思います。
現状について言及するとき、問題文にリンクしている必要があると私は思います。
例えば問題文に、『地震による災害』と書いてあれば、『南海トラフ沖地震の発生確率』に言及しますし、
『豪雨による災害』と書いてあれば、『岡山県の内水氾濫』に言及します。
問題文を読んでいることをアピール!
※どうしても一致するものが書けなければ、妥協して周辺知識にしてもよいと思います。
筆者が不適当と思う課題
たいていの問題は、『人手不足』『予算不足』から来ます。
この問題に対して、
『移民政策を進め人手を増やす』や『国から地方自治体予算をつける』といった課題を上げるのは
2つの観点から不適当だと考えています。
■1つ目の観点
まず、(1)では技術者としての立場で 課題の立案を求められています。
移民政策や国から予算をつけるというのは行政の役割であり、
技術士試験で技術者の求められている役割ではないと考えられるからです。
■2つ目の観点
たいていの問題は、『労働力・資金などのリソースが限られている』ために生じます。
技術士試験はその限られたリソースを配分することによって、
問題を解決できるかを問うています。
その問題において、
『リソースを増やす』
という回答は、問題解決能力を示すという観点から、
不適切となります。
個人的な意見になりますが、
(1)でこのような回答をするのは避けた方が良いでしょう。
筆者が思う(1)の答案構成
私が思う(1)の答案構成は
1.〇〇のための課題
(1)課題A 【タイトル+6~7行】
現状⇒問題⇒課題⇒導入効果
したがって、〇〇性の観点から、『課題A』が課題である。
(2)課題2~3 ※以下同じ
という構成が良いのではないかと思っています。
コンピテンシーとの関係
【専門的学識】【問題解決】をアピールしましょう!
詳細は、下記に記載しています!
⑥技術士(二次試験) 筆記試験の勉強法・コンピテンシーと採点基準 | 社会人向け資格の寺子屋 (sk-pe-t.jp)
まとめと他の記事のご紹介
この記事をお読みいただいたことで、
選択Ⅲ、問題文と課題、観点の記載方法などを理解していただけたと思います。
他の記事では、
(2)最も重要な課題と解決策
についても紹介していきますので
参考にしていただければと思います。
コメントを残す